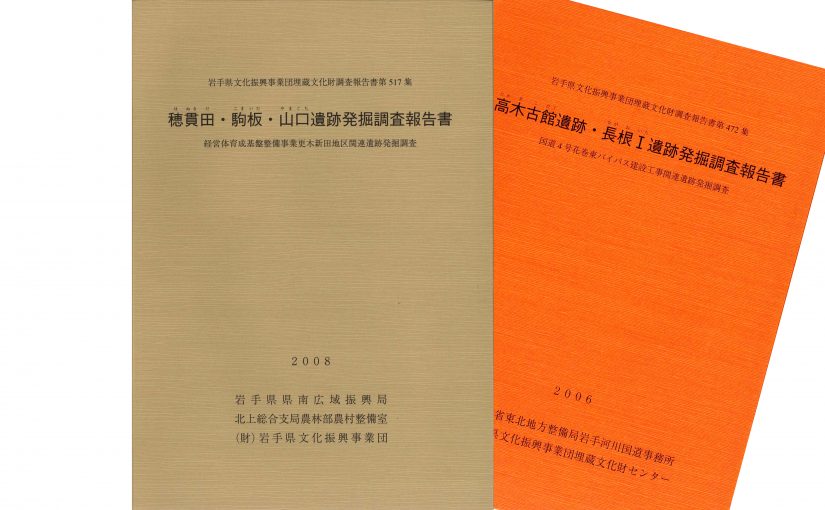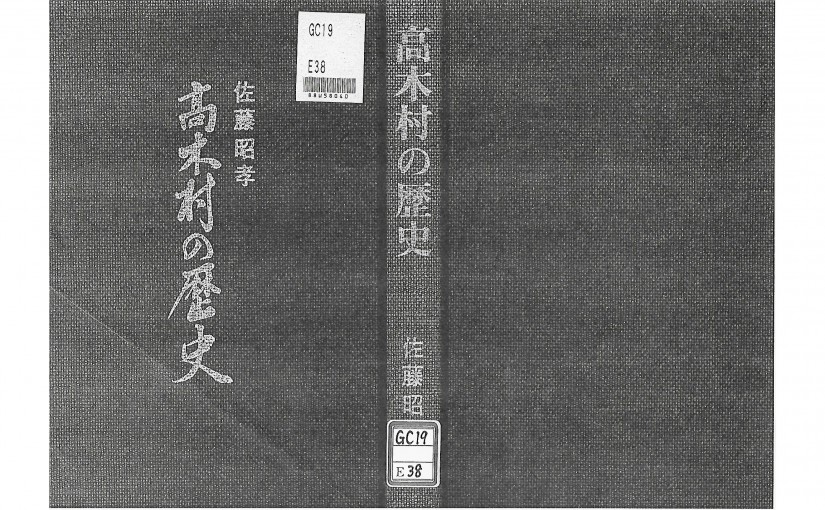「東十二丁目誌」の第2章・第5節「東十二丁目の遺跡」には「高木村の歴史」(注1)から引用して、大沢(一)(集落跡 縄文・平安)、大沢(二)(集落跡 縄文・平安)、小袋(集落跡 平安)、そして薬師堂(館跡 平安)と4ヶ所の遺跡を挙げ、「縄紋時代の遺跡の分布では、北上川東岸の河岸段丘沿いが多いと云われているが、当地域にも地形的に考えてまだ確認されず地中に眠っているものも相当にあるように思われる。」と付言しています。
少し調べてみて驚きました。東十二丁目は「遺跡の郷」の様相を呈しています。平安時代以前のものだけで13ヶ所、人家のあるところの大半が遺跡(公式には「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言うようです)に含まれているのです。 続きを読む 「東十二丁目誌」註解覚書(5) -遺跡-