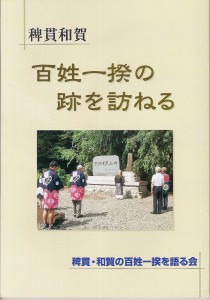(石崎直治著・発行「東十二丁目誌」(H2.2.28)より)
「村里は用地の開発により、用地は用水による」と云われるが、開拓の歴史を考える時、郷土の先人達が多くの困難と戦いながら、工事と取組み、築造し、管理し、修理を重ねながら長年代々にわたって受継がれて来ていることがわかる。
私達の村落は、北上山系と北上川の間に存在する集落であるが、南端にある猿ヶ石発電所から山麓にそうて北に進む時、2~300m間隔位に山から沢水が流れ落ちていることに気がつく、そしてそれぞれの沢には小さい俗に山田と称される不整形の水田が棚田となって耕作されている。その沢を登ると大ていはそこに昔使われたであろう堤が確認される。 続きを読む 東十二丁目の水利 – 堰以前 –